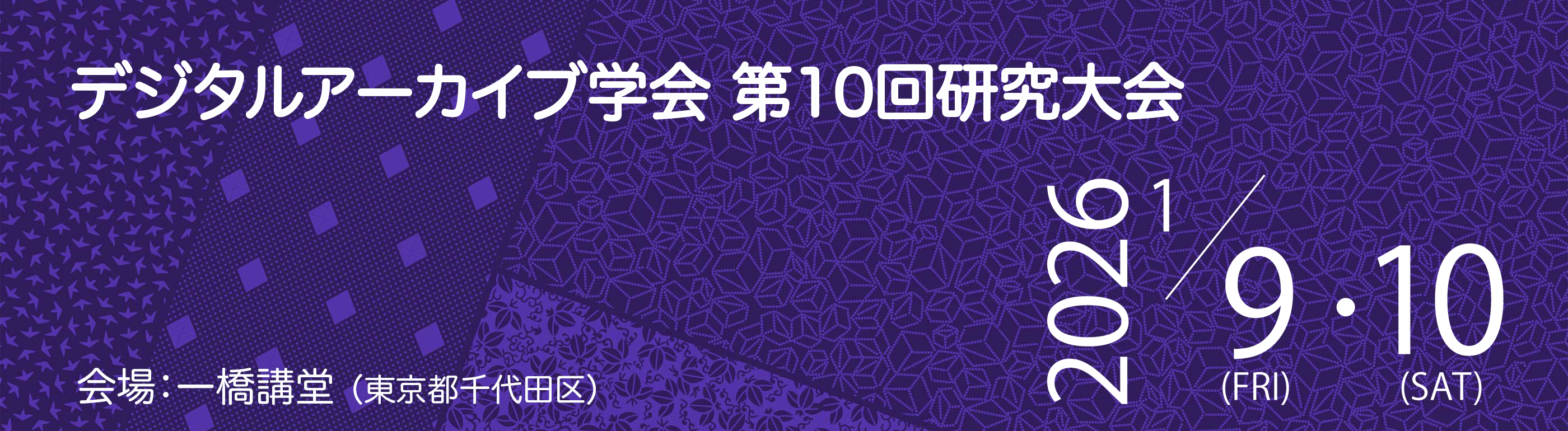デジタルアーカイブにおけるキュレーションの現在地
| 日時 | 1月9日 10:30~12:00 |
| 会場 | A会場 |
| 運営責任者 | 太下 義之 / 緒方 靖弘 |
| 協力 | 産業とデータ・コンテンツ部会 |
| 登壇者 | 導入/趣旨説明:後藤 和子(同志社大学) ・阿辺川 武(東京大学大学院教育学研究科/NPO連想出版) ・金子 晋丈(慶應義塾大学 情報工学科 准教授) ・久永 一郎(大日本印刷株式会社 ヒューマンエンジニアリングラボ 室長) ・本間 友(慶應義塾大学 ミュージアムコモンズ 准教授) 司会/モデレーター:太下 義之(理事/産業とデータコンテンツ部会長) |
| 概要 | デジタルアーカイブはユーザーに活用されて初めて産業化します。デジタルアーカイブ をいかに組み合わせ、どのような付加価値をつけてユーザーに届けるのか、デジタルアーカイブにおけるキュレーションの現在地と今後の可能性について、産業化の観点から議論します。 |
地域文化を可視化する―市民協働とデジタルアーカイブ―
| 日時 | 1月9日 10:30~12:00 |
| 会場 | B会場 |
| 運営責任者 | 前川 道博 |
| 協力 | 地域アーカイブ部会 |
| 登壇者 | <登壇者> 森 啓(いしはらの里・むかしを語る会) 石田 茂富(岐阜女子大学大学院) 楠瀬 慶太(高知工業高等専門学校) <以下討論から参加> 井上 透(岐阜女子大学) 小山 元孝(福知山公立大学) <進行> 楠瀬 慶太 |
| 概要 | 地域にはアーカイブ化して継承していくべき民間所在資料が多数存在する。これらを継承する方法論の一つがデジタルアーカイブによる可視化である。それらを実現するためには所蔵者や住民といった市民と公的機関、研究者との協働が重要になる。本セッションでは地域文化のデジタルアーカイブに取り組む市民の視点から取り組みを整理し、市民参加による地域文化の記録と継承の在り方を問い直してみたい。 地域アーカイブに取り組む市民や市民団体の報告をベースに、研究者との討論を通して論点整理を行いたい。 【報告1】森 啓(いしはらの里・むかしを語る会)「石原の文化資源ノート―高知県土佐町の住民団体による地域アーカイブ活動」 【報告2】石田 茂富(岐阜女子大学大学院)「遺品の中からの地域資料採掘―『デジタルアーカイブ化への前工程を、地域の人たちと協働する』の中間報告―」 【報告3】楠瀬 慶太(高知工業高等専門学校)「市民協働による地域デジタルアーカイブの課題と可能性―10年の試みの中から―」 【討論】「地域文化を可視化する―市民協働とデジタルアーカイブ―」井上 透(岐阜女子大学)、小山 元孝(福知山公立大学)、森 啓、石田 茂富 進行:楠瀬慶太 |
DA and Education for AI / AI for DA and Education
| 日時 | 1月9日 10:30~12:00 |
| 会場 | C会場 |
| 運営責任者 | 大井 将生 |
| 協力 | S×UKILAM連携 |
| 登壇者 | 浅間 原子 (泉大津市楠小学校 校長) 荒木 真歩 (デジタル庁 国民向けサービスグループ 統括官付参事官付主査) 江草 由佳 (国立教育政策研究所 研究企画開発部教育研究情報推進室 総括研究官) 大井 将生(同志社大学 文化情報学部 准教授) 宮田 諭志 (成城学園初等学校 教諭) |
| 概要 | デジタルアーカイブ(DA)は構築と活用の輪を形成することが肝要である。とりわけ教育活用に関しては、各地域において未来を担う子どもたちを育む知の基盤としてDAの重要性が認識されている。教育現場でも、情報化の進展やパンデミックを背景として、GIGAスクール構想による1人1台端末の実現など、ハード面での教育DX化が進みつつある。さらに、AIの台頭やフェイクニュースの蔓延などを鑑み、情報への批判的思考力を育む必要性が高まっている。こうした社会的な背景や課題をふまえ、今後ますますDAの教育活用への期待が高まっていくことが予想される。 一方で、教育現場におけるDAの普及や活用方法の検討・課題の共有については、未だ十分に為されているとは言い難い。そこで本セッションでは、「DAと教育」に関する多様なアクター、専門家が一堂に会し、それぞれの立場からDAの教育活用の現在と未来について情報を共有し、議論する場を創出する。本学会の研究大会において「教育」にフォーカスするセッションの開催は昨年度から始まったばかりの新しい試みであり、学会をあげて当該分野の学術的な発展及び新しい教育の構築が期待されている。 |
デジタルアーカイブ推進基本法は現場とアーカイブ支援をどう変えるか
| 日時 | 1月9日 10:30~12:00 |
| 会場 | E会場 |
| 協力 | 法制度部会 |
| 運営責任者 | 寺田 遊 |
| 登壇者 | ■パネルディスカッション(敬称略・50音順) ・赤松 健 (参議院議員) ・石川 和子 (日本動画協会理事長・DAPCON会長) ・黒橋 禎夫 (国立情報学研究所所長・デジタルアーカイブ学会会長) ・宍戸 常寿 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) ・森 いづみ (県立長野図書館館長) ・笠 浩史 (衆議院議員) 司会:福井 健策 (弁護士・デジタルアーカイブ学会副会長・同法制度部会長) ■来賓挨拶 中原 裕彦 (内閣府知的財産戦略推進事務局長) |
| 概要 | 「この国のデジタルアーカイブには、常にヒト・予算・権利の3つの壁がある」 「活動は個人の情熱に依存して孤立し、政府には横断的な推進母体も支援の国家プランもない」 「だから、デジタルアーカイブ推進基本法を作ろう」 それがデジタルアーカイブ学会を立ち上げたメンバーの思いでした。 推進基本法の議論は2017年の学会立上げと共に高まりますが、諸情勢から足踏みを余儀なくされます。しかしこの間に国の取組も進み、学会でも二度の政策提言で常に推進基本法への声を政府・議員に届けて来ました。 そして今再び、推進基本法の成立に向けた熱気が高まっています。実現すれば各種のデジタルアーカイブ活動への支援や連携は、飛躍的に高まる可能性があります。 もっとも推進「基本」法ですから推進母体の顔ぶれや推進計画の内容が重要です。 推進対象のアーカイブとは?推進母体は官主導か官民連携か。縦割りをどう打破するか。地域アーカイブの支援組織をどう立ち上げるか。オープンデータ政策との連携、人材育成の設計、AIとの向き合い方、権利者不明や肖像権など権利問題の解決はどうなるのか。キーパーソンを招き法成立をにらんだ設計論議を展開します。 |
| リンク | https://hoseido.digitalarchivejapan.org/symposium/ |
デジタルアーカイブ価値化に向けた多層的アプローチ
| 日時 | 1月10日 10:00~11:30 |
| 会場 | C会場 |
| 運営責任者 | 嘉村 哲郎 |
| 登壇者 | 後藤 博之(Atomos-Seed LLC代表 / フードNFTコンソーシアム 共同代表/ NPO法人 NEM技術普及推進会NEMTUS理事長) 嘉村 哲郎(東京藝術大学芸術情報センター) 柿野 耕平(九州大学 経済学院 マネジメント部門) 伊東 謙介(東京大学ブロックチェーンイノベーション寄付講座 特任研究員 / アーティスト ) |
| 概要 | 現代社会において、デジタルアーカイブ(以下、DA)は人類の知的・文化的資産を保存・継承する基盤として、その重要性を一層高めている。しかしながら、DAは長期的な存続可能性や社会的意義をめぐる構造的課題に直面している。 こうした課題の背景には、近年の情報通信技術やWeb技術の急速な進展がある。これらの技術的変化は、DAの概念を保存を基盤とする段階から、コミュニティ主導による「価値創造の場」へと発展させる可能性を開いている。 本企画では、登壇者4名がそれぞれの専門領域から、DAをめぐる技術的・実践的・哲学的課題を考察し、今後の新たな枠組みを構想するための視点を提示する。これにより、学術的・実践的議論を通じてDAの転換を促すことを目的とする。 ■「デジタルアーカイブ価値化に向けた多層的アプローチ」 報告1:嘉村 哲郎「DAの価値表現と価値の⾃律性-基盤的視点より」 報告2:後藤 博之「ブロックチェーンによる単一障害点SPOFを排除した長期保存と、DAOによる価値と貢献の循環」 報告3:柿野 耕平「タイトル未定」 報告4:伊東 謙介「自律分散的に引用関係を決める—Bitcoin Protocolから考えるDAの転換」 |
パブリックドメインになった映像に対するアーカイヴィングの現状と課題
| 日時 | 1月10日 10:00~11:30 |
| 会場 | D会場 |
| 運営責任者 | 藤岡 洋 |
| 登壇者 | 米野 みちよ(静岡県立大学) 岡田 泰平(東京大学) 藤岡 洋(京都大学) 村山 英世(記録映画保存センター) 浜崎 友子(記録映画保存センター) 井上 将治(NHK国際放送局) |
| 概要 | 映像を学術資料化しようとするとき、アーカイブ構築は有効な手段の一つである。本企画チームが取り組む「1930年代に日本人商人が残した戦前フィリピンの映像・写真・文書の再資料化研究」は、当時の映像に文書・写真・音声など多種にわたる資料群を、学術的検証を行いつつ、関連づけていくことでそれぞれの情報を正規化しようとする試みである。 本企画では、次の二つの課題を論じる。一つは、パブリックドメインにあるデジタル資料を公共の文化遺産ととらえ、公共の知を取りこみながら研究する際に生じる課題。もう一つは、研究成果の二次活用という課題である。これらの課題に対して、多様な立場のアクターとともに、歴史的な映像資料や研究成果を文化資産として現地へ還元したり、広く社会で活用する方法について、積極的な議論を促したい。 (本企画は JSPS科研基盤(B) 24K03167 ならび JSPS科研基盤(C) 25K04659 の助成を受けている) |